- 7月 16, 2025
- 10月 6, 2025
【違いを解説】「訪問診療」と「往診」、どちらを頼めばいいの?

「訪問診療」と「往診」という言葉を耳にすることはあっても、その違いを明確に理解している方は少ないかもしれません。どちらも医師がご自宅などに訪問して診察を行う点では同じですが、実は医療サービスとしては全く異なるものです。
神戸市西区のさいとう内科クリニックでは、患者様が住み慣れた場所で安心して療養できるよう、きめ細やかな在宅医療を提供しています。ここでは、「訪問診療」と「往診」それぞれの特徴と、どのような場合にどちらを選べば良いのかを詳しく解説します。
「訪問診療」と「往診」の違いをズバリ解説!

在宅医療は、医療上の必要性により、在宅での診療が必要な場合に実施されるものです。大きく分けて「訪問診療」と「往診」の2種類があります。この二つのサービスは、患者さんの状態やニーズに応じて使い分けられます。
訪問診療とは?
訪問診療とは、病状の悪化を事前に防ぐことを目的に、計画的かつ定期的に医師や看護師が患者さんのご自宅や施設を訪問し、診察や処方、健康管理を行う医療サービスです。通常は月2回ほどの訪問となります。これは、外来診療が困難な在宅療養中の患者さんに対し、継続的な医療を提供するために行われるものです。
さいとう内科クリニックの訪問診療では、月に1回または2回の訪問を基本とし、以下のような目的で計画的に医療を提供します。
- 病気の治療と管理: 定期的な診察を通じて、血圧や定期薬の管理と処方などを行います。診察、検査、注射、処置、薬の処方などの治療も行います。これは、慢性疾患の管理や病状の安定化に不可欠です。
- 病状悪化の予防: 転倒や寝たきり状態、肺炎、褥瘡(じょくそう)の予防、栄養状態の管理など、予測されるリスクを回避し、入院が必要な状態を未然に防ぎます。これにより、患者さんの生活の質(QOL)を維持・向上させ、ご家族の介護負担を軽減することにも繋がります。
- 長期的な療養支援: 患者さんやご家族と相談しながら診療計画を立て、安心して自宅で療養できるようサポートします。生活環境に合わせたきめ細やかなアドバイスや指導も行い、より良い在宅療養環境の構築を目指します。
往診とは?
一方、往診とは、急変対応などを目的に、患者さんやご家族からの依頼に基づいて医師がその都度、臨時的に診察に伺うことを指します。
例えば、「急に熱が出た」「体調が急変したけれど、救急車を呼ぶほどではない」といった場合に利用する、いわば「緊急時の手段」です。往診は診療上必要であると認められる場合に行われます。訪問診療を受けている患者さんが訪問予定日でない日に急に具合が悪くなり、医師に来てもらったような場合は、「往診」を受けることになります。
さいとう内科クリニックによる往診は、当院かかりつけの患者さんから、診療時間内にご依頼があった場合に行っております。初診の患者さんには往診を行っておりませんのでご注意下さい。初診の患者さんは、まず、当院の外来を受診していただき、当院をかかりつけ医としていただけましたら、以後の往診は可能になります。
なぜ在宅医療のニーズが高まっているの?
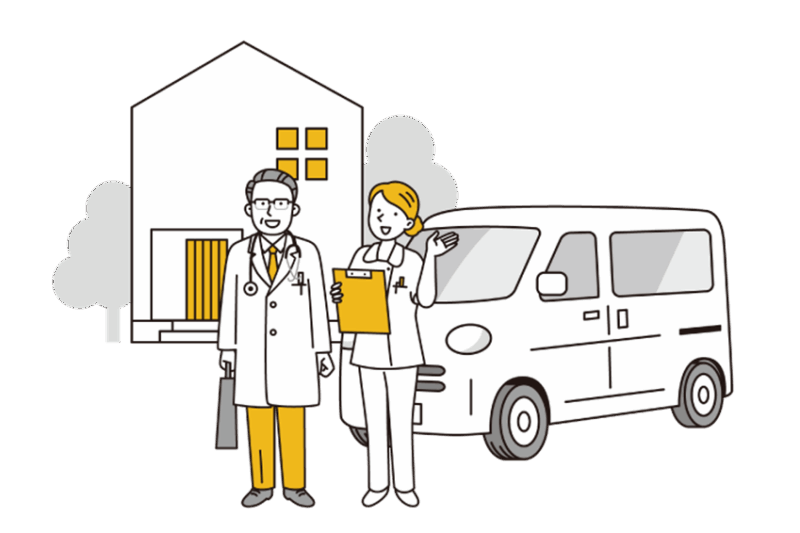
近年、日本において在宅医療のニーズが急速に高まっています。その背景には、社会構造の変化と国民の意識の変化が大きく影響しています。
日本の年間死亡者数は、高齢化に伴い年々増加傾向にあります。厚生労働省のデータによると、1995年には90万人台だった死亡者数は、2003年には100万人を超え、2022年には150万人台に達しています。今後もしばらく増加が見込まれており、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、ピークにあたる2040年には年間167万人が亡くなると想定されています。
ここで注目すべきは、亡くなる場所の変化です。太平洋戦争直後の日本では、自宅で亡くなる人が80%以上を占めていましたが、その後病院で亡くなる人が増え、1976年には病院死が在宅死を上回りました。2000年には病院で亡くなる人の割合が81%に達し、他国(スウェーデン42%、オランダ35%、フランス58%など)と比べても顕著に高い状況でした。
しかし、近年、国民の意識は変化しつつあります。厚生労働省が2017年に実施した「人生の最終段階における医療に関する意識調査」では、末期がんへの罹患を想定した場合に医療・療養を受けたい場所について、47.4%の人が「自宅」と回答しています。このうち69.2%の人は、最期を迎えたい場所にも「自宅」を選んでいました。2000年以降、自宅で亡くなる人の割合は13%前後で推移していましたが(コロナ禍の2020年以降は15~17%に増加)、病状や家庭の状況によるとはいえ、在宅医療への高いニーズがうかがえます。
また、病床数の観点からも在宅医療の重要性が増しています。日本は人口1,000人当たりの病床数が13.0と、諸外国(アメリカ2.9、カナダ2.5など)と比べても高い水準にあります。医療費抑制の観点から、病床数の削減も検討されており、自宅で終末期を迎えられる患者さんが病床を利用し続けると、真に病床での対応が必要な患者さんへの医療が手薄になる可能性も指摘されています。
このように、死亡者数の増加や患者さんの自宅療養ニーズの高まり、そして病床数削減といった情勢の中で、在宅医療は今後ますます必要性が高まると言えるでしょう。
どちらを選べばいいの?「訪問診療」が向いている方
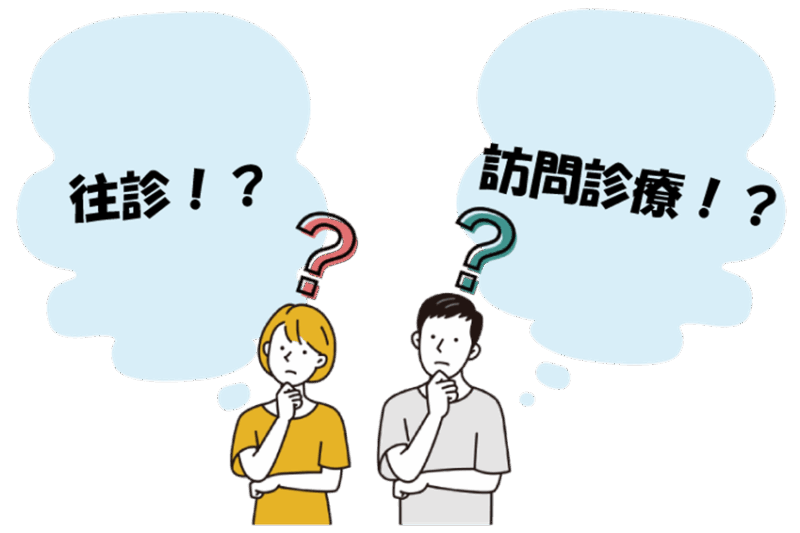
それでは、具体的にどのような方が訪問診療の利用を検討すべきなのでしょうか。さいとう内科クリニックの訪問診療は、特に以下のような方におすすめです。
医療機関への通院が困難な方
- 移動や外出、病院での待ち時間が困難な方: ご高齢で体力的な負担が大きい方、車椅子や歩行器を利用されている方、または寝たきりの方など、ご自身で医療機関へ足を運ぶことが難しい方が対象です。
- 認知症の方: 認知症の症状により、慣れない環境での受診が困難な方や、付き添いの方の負担が大きい場合にも適しています。
在宅での療養を希望される方
- 住み慣れたご自宅で安心して療養したいと希望される方: 病院ではなく、ご自宅という安心できる環境で治療を受けたい、療養を続けたいという方に最適です。
- 退院後の継続的なケアが必要な方: 病院を退院した後も、定期的な医療管理や処置が必要な場合に、ご自宅で専門的なケアを受けることができます。
特定の疾患や状態をお持ちの方
- 寝たきりの方: 全身状態の管理、褥瘡(じょくそう)の予防と処置、栄養管理など、専門的なケアが自宅で受けられます。
- がん末期、神経難病、重度障がいの方: 緩和ケアや疼痛管理、生活の質の維持・向上を目的としたきめ細やかな診療が可能です。在宅での看取りを希望される場合のサポートも行います。
- 慢性呼吸器疾患で在宅療養が必要な方: 在宅酸素療法や呼吸状態のモニタリングなど、専門的な呼吸器管理を自宅で行います。
- 胃ろうや尿道カテーテルを使用している方など: 医療器具の管理や交換、感染症予防など、日常的な医療処置が必要な方に継続的なサポートを提供します。
- 脳梗塞などの後遺症がある方や、高血圧症、糖尿病、高脂血症などの慢性疾患をお持ちで、自宅での継続的な管理が必要な方も、定期的な診察と薬の処方で病状を安定させることができます。
ご家族の通院付き添いの負担が大きい方
- ご家族が仕事や介護などで忙しく、患者さんの通院に付き添うことが難しい場合でも、医師や看護師がご自宅に訪問するため、ご家族の負担が軽減されます。
24時間365日の緊急時対応が必要な方
- 万が一の急変に備え、夜間や休日でも医師や看護師によるサポート体制を望む方に、安心感を提供します。
自宅での看取りを希望される方
- 住み慣れたご自宅で、ご家族に見守られながら最期を迎えたいという希望を尊重し、疼痛緩和や精神的なサポートを含めたターミナルケアを行います。
入院を避けたい、延命治療は希望しない方
- ご自身の意思で、自宅での療養を優先したいと考えている方に、その希望に沿った医療を提供します。
さいとう内科クリニックの訪問診療の特長
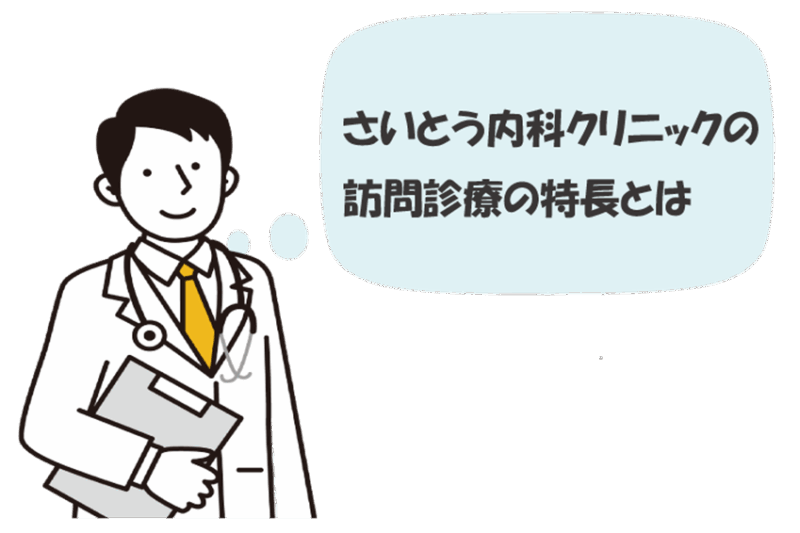
さいとう内科クリニックでは、患者さんが安心して在宅医療を受けられるよう、様々な体制を整えています。
専門的な視点から質の高い医療
当クリニックには、内科全般(総合内科・循環器・糖尿病など)について、幅広い疾患に対応可能です。これにより、複数の疾患をお持ちの患者さんに対して、総合的かつ専門的な視点から質の高い医療を提供できます。例えば、糖尿病を患う高齢の患者さんが心疾患も抱えている場合や、認知症による精神的な不調がある場合など、多角的なアプローチで対応いたします。
24時間365日体制の安心サポート
医師に加え、連携している訪問看護ステーションの看護師による24時間体制を整えています。定期訪問だけでなく、緊急時には看護師からのアドバイスや駆け付け、医師の往診、さらには入院先の手配まで、きめ細やかに対応します。患者さんの状態が急変した場合でも、迅速に状況を把握し、適切な処置や判断を下すことが可能です。入院が必要になった場合も、患者さんのご希望やこれまでの入院履歴を考慮し、連携病院への紹介搬送を優先します。また、救急搬送先として様々な病院と連携しており、いざという時にも安心できる体制を構築しています。
幅広い医療処置・管理が可能
ご自宅での診察だけでなく、以下のような幅広い医療処置や管理が可能です。これにより、入院せずに自宅で専門的な医療ケアを受けることができます。
- 定期的な医師による診察(血圧や定期薬の管理と処方など)
- 各種検査(血液検査や尿検査、腹部エコー)
- 各種薬剤の注射や点滴
- 気管内吸引
- 在宅酸素療法の管理
- 脳卒中(脳梗塞・脳出血)などの継続的加療
- 褥瘡(じょくそう)の処置、創傷処置
- 高血圧症・糖尿病・高脂血症などの慢性疾患に対する継続的加療
- 認知症・神経症・不眠症の加療
- 浣腸・摘便
- 心臓疾患やペースメーカー装着の方の継続的加療
- 予防接種(インフルエンザ・コロナワクチン)
特に以下の4つに該当される方は、専門的な管理が必要となるため、ぜひご相談ください。
- がん末期などのターミナルケア、在宅での看取り
- 経管栄養(胃ろう)の管理
- 尿道カテーテルの管理や導尿
- 人工肛門の管理
在宅医療を取り巻く最近の動向
在宅医療は、高齢化が進む日本において、ますますその重要性を増しています。近年、国も在宅医療の推進に力を入れており、様々な動向が見られます。
在宅療養支援診療所/病院の役割強化

かつて在宅医療は、かかりつけ医が通常の診療の延長線上で行うケースが一般的でした。しかし、在宅医療が看取りまで含むようになり、24時間体制が必要となることから、近年は在宅医療に積極的に取り組む「在宅療養支援診療所(在宅専門診療所)」や「在宅療養支援病院」が増えています。
国は在宅医療の提供体制を整備するため、2016(平成28)年度の診療報酬改定を機に、これらの在宅療養支援施設の新規開設を認めました。これらの診療所は外来対応をほとんど行わない分、通常のクリニックと比べて開業スペースや資金が少なく済むといった特徴もあります。在宅医療を専門とする医師が複数名在籍しているため応需体制が常時取りやすく、患者さんにとっても、より質の高い、安心できる在宅医療を受けられるというメリットがあります。
診療報酬においても、往診料に係る加算は在宅療養支援施設の方が高くなる仕組みが設けられています。2024(令和6)年度の診療報酬改定では、在宅医療におけるICTを用いた連携の推進や、地域における24時間の在宅医療提供体制の推進を目指す上で、在宅療養支援施設が担う役割がますます重視されています。各保険医療機関との連携が求められるほか、「往診時医療情報連携加算」の新設も予定されており、地域全体で在宅医療を支える体制づくりが進められています。
コロナ禍における往診サービスの拡大と今後の展望

2020年以降の新型コロナウイルス感染症の流行は、在宅医療、特に往診サービスに大きな影響を与えました。感染リスクを抑えるための「受診控え」が生じたことで、スマートフォンアプリなどを介して往診を依頼するサービスが急速に拡大しました。特に小児医療では、医療費助成制度が適用されることから、少ない自己負担で利用できる点が利用者を増やしました。
新型コロナウイルス感染症そのものに対しても、往診サービスは重宝され、医療機関を受診しなくても診断や治療を受けられたり、自宅療養に対応してもらえたりと、多くの患者さんがその恩恵を受けました。2020年11月には、ある往診サービスが前月比144%と大きく利用者数を伸ばしたというデータもあり、そのニーズの高さが伺えます。自治体と提携し、地域の医療提供体制の整備に協力した事例も多数ありました。
しかし、2023年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行し、2024年4月には治療や入院に対する公費負担が終了するなど、社会状況が変化する中で、往診サービスを巡る環境も変わってきています。
2024年度の診療報酬改定では、「患者さんの状態に応じた適切な往診の実施を推進する観点」から、往診に関する評価が見直されました。もともと定期的な訪問診療をしていない患者さんに対しては、往診料が大幅に引き下げられることになったのです。緊急往診加算や夜間・休日往診加算、深夜往診加算を得るためには、日ごろから訪問診療を受けているか、地域の関係施設と連携しているかといった条件が課されるようになりました。
この改定は、一部の往診サービスにとっては逆風となり、サービス終了を発表する企業も現れました。サービスを継続している企業も、医師への報酬の見直しを迫られる可能性があります。さらに、2024年度から医師の働き方改革が始まったことで、往診サービスへ協力する医師の労働力は減っていくと予想されます。診療報酬改定による「賃金引き下げ力」と、働き手不足による「賃金上昇力」の両者がどのような結果を生むのか、今後の在宅医療の動向が注目されます。
訪問診療の対象エリアと費用について
訪問エリア

さいとう内科クリニックの訪問エリアは、当クリニックを中心として、半径16kmの範囲となります。神戸市西区、垂水区、明石市、加古郡稲美町が含まれます。
診療費用について
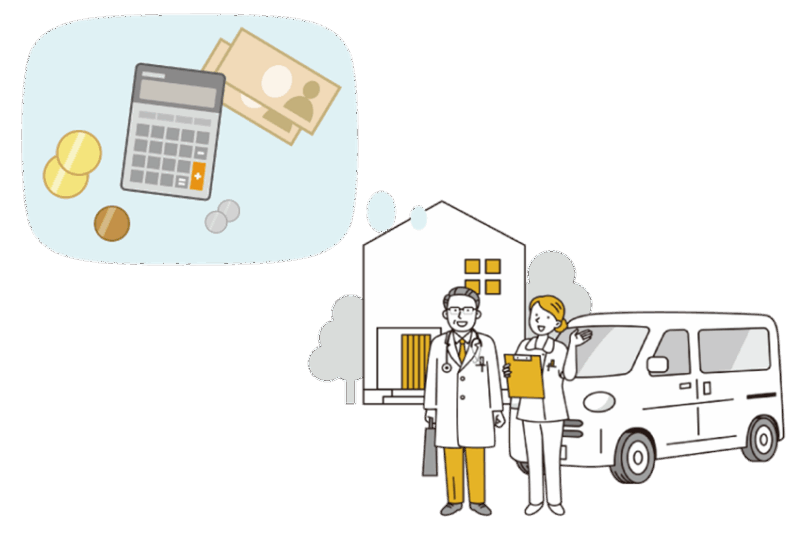
訪問診療にかかる費用は、各種健康保険が適用となり、入院・通院の時と同じ負担割合になります。例えば、後期高齢者医療制度の被保険者であれば、原則として1割または2割負担となります。また、訪問診療は外来診療よりも診療報酬が高く設定されており、貴重な医療資源をより多く必要とする特性が反映されています。さらに、訪問にかかる交通費は距離に応じて自費請求となりますので、ご理解をお願いいたします。詳しい料金体系や個別の費用については、直接お問い合わせいただければ、詳細をご説明させていただきます。
訪問診療開始までの流れ

さいとう内科クリニックの訪問診療をご利用いただくまでの流れは以下の通りです。患者さんやご家族が安心してサービスを開始できるよう、丁寧な説明とサポートを心がけています。
1 お問い合わせ
まずは当クリニックまで、お電話にてお問い合わせください。患者さんの現在の症状や状況を簡単に伺い、訪問診療が適用可能かどうかの初期確認を行います。お問い合わせは診療時間内にお願いいたします。
2 ご説明・ご相談
お問い合わせ後、診療時間内に、当クリニックにご来院ください。訪問診療のサービス内容について詳しくご説明させていただきます。この段階で、患者さんご本人、またはご家族の方にご納得いただけるまで丁寧にご案内し、疑問点や不安な点に全てお答えします。患者さんのご希望や生活状況を詳しくお伺いし、最適な診療計画のベースとなる情報を共有させていただきます。
3 お申込み
当クリニックの訪問診療について十分ご理解・ご納得いただけましたら、正式にお申し込みください。この際、診療内容に同意いただき、当クリニックとの契約を交わしていただきます。現在治療中の方は、前医に紹介状の作成を依頼してください。これまでの診療情報をいただくことで、よりスムーズに連携し、適切な医療を提供できます。
4 訪問診療スケジュールの作成
面談内容を踏まえ、当クリニックの医師が訪問診療のスケジュールを作成します。患者さんのご希望に応じ、診療内容や訪問回数などを詳細に設定していきます。例えば、週に1回、2週間に1回など、患者さんの病状や生活リズムに合わせた無理のない計画を立てます。
5 訪問診療の開始
作成したスケジュールに基づいて、いよいよ訪問診療を開始いたします。定期的に医師や看護師がご自宅や施設に伺い、患者さんの健康をサポートさせていただきます。現在専門科にかかられている方は、当クリニックの訪問診療との併用も可能ですし、当クリニックに一本化していただくことも可能ですので、ご相談ください。

さいとう内科クリニックは、医療を必要としているのに疾患や加齢などの影響で通院できない方々をサポートしています。患者さんが安心してご自宅で暮らすためには、ご家族の存在と共にケアマネージャー様との連携も欠かすことができません。
当クリニックは、患者さんご本人とご家族の意思を尊重し、信頼できるケアマネージャー様のプロとしての知見も大切にしながら、関係する皆様としっかりと話し合い、適切な診療の提供に努めています。
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

- 院長
- 斉藤 雅也
- 診療内容
- 内科・消化器科
- 住所
- 〒651-2412
兵庫県神戸市西区竜が岡1-15-3(駐車場18台あり)
(旧:森岡内科医院) - 電話
- 078-967-0019
- 携帯
- 080-7097-5109
- 電車
- JR山陽本線「魚住駅」から車で約9分
JR山陽本線「大久保駅」から神姫バス天郷停留所(約11分)下車、徒歩5分 - 車
- 第二神明道路大久保インターから約1分
- 駐車場
- 駐車場18台完備!
